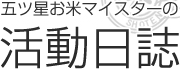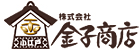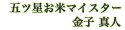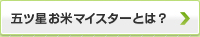カテゴリー
お店からのお知らせ
- 1月7日 「七草」粥で健康祈願!2026
- 2026年1月6日
- 謹賀新年 本年もよろしくお願いいたします。
- 2025年12月31日
- 今年もありがとうございました!2025
- 2025年12月30日
- 年内お届け!お年賀・帰省のお土産に
- 2025年12月28日
- お正月「のし餅」28日分 入荷しました
- 2025年12月27日
お茶漬け(お米料理)
2010年09月04日
茶漬けのはじまりは平安時代、夏には「水飯」といい飯に冷水をかけて食べ、ふつうは「湯漬け」といってただのお湯をかけて食べていたそうです。
室町時代になると、特に湯漬けが盛んになり一般に普及しました。
室町後半から江戸時代にかけては、湯漬け、茶漬けともに平行して行われていましたが、煎茶の普及にともなって茶漬けだけが生き残っていきます。
これは冷たいご飯に熱いお茶をかけて、残り物や漬け物をつけて食べるような簡単な食事で、茶漬けは貧しい食事の意でした。
江戸時代後期には「茶漬け屋」もあらわれて、それこそ簡単な食事を食べさせてくれたという。これが繁盛して、やがて豪華な茶漬けを出す店も出てきました。
茶漬けには海苔やごま塩、塩コンブ、みそ漬け、佃煮、干物や塩ざけ、タイ、ヒラメ、貝柱、ウナギのかば焼きなどが使われますが、明治・大正時代の東京では、塩せんべいを割って茶漬けの具に使う人もいたそうです。
いま高級茶漬けとして料理屋で出てくるものはタイや、マグロ、また鶏肉などを使っただし汁茶漬けです。
使う具の名前で鯛茶漬け、鮭茶漬け、海苔茶漬け、天ぷらを使った天茶漬け、ウナギのかば焼きを使ったうな茶漬けなどと呼んでいます。