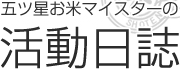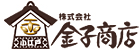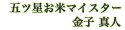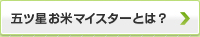カテゴリー
お店からのお知らせ
- お米の定期便(3回コース)受付中!
- 2025年12月15日
- 杵つき「のし餅」予約受付中【12/20迄】
- 2025年12月6日
- 【新米入荷】山形つや姫 令和7年産
- 2025年12月5日
- おいしいお米を海外に!Xmasプレゼント
- 2025年12月4日
- 新米予約 「山形おきたま産つや姫」令和7年産
- 2025年12月3日
稲作は日本の風土にピッタリ(お米の歴史)
2010年09月11日
栽培方法はどうやって学んだのか?
米は、日本への移住者たちが日本へ持ち込んだのだということまではわかってきました。その作り方も、初めは彼らに学んだのでしょうか。

米はおいしかった!
その頃の食生活からすると、初めて食べた米はおいしかったし、お腹もいっぱいにしてくれたのではないでしょうか。
そこで、稲作をしよう、米を作ろう!と考えるのは当然のことです。
水の中に根を下ろして生育する稲は、温暖多湿(アジアモンスーン気候)な日本の風土にぴったりと合い、どんどん米が収穫できるようになったのです。
ごはんを主食として魚や野菜を副菜とする食事の形は安土桃山時代には定着したといわれています。
当時、富裕層はお米を食べていましたが、庶民にはまだまだ行き渡らずヒエ・アワ・ソバ等の雑穀を食べていました。
だれもがお米を今のように食べられるようになったのは明治以降のことのようです。
工夫上手な日本人
自然にできる米を、工夫の得意な日本人たちは工夫に工夫を重ねて収穫量を増やし、卑弥呼の時代の終わりごろには現在と同じような稲の栽培、つまり、
苗を育てて水を張った田んぼに植えて収穫する方式が確立していたのではないかといわれています。
現在に至るまで、様々な品種改良の結果、寒い北海道でもたくさんおいしい米が収穫できるようになり、日本は、世界でも米が一番おいしいしい国として認められるようになっています。