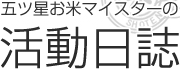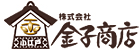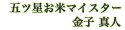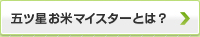カテゴリー
お店からのお知らせ
- 【新商品】出雲のおもてなし(お赤飯・鯛おこわ)
- 2025年12月22日
- お米の定期便(3回コース)受付中!
- 2025年12月15日
- 杵つき「のし餅」予約受付中【12/20迄】
- 2025年12月6日
- 【新米入荷】山形つや姫 令和7年産
- 2025年12月5日
- おいしいお米を海外に!Xmasプレゼント
- 2025年12月4日
「炊き込みごはん」の歴史
2006年04月06日
炊き込みごはんは、米の収穫が十分でなかった頃、米を節約するために色々な具を混ぜて炊いたのが始まりです。
欧米諸国など、穀物としては主に小麦を原料とした食べ物を食べている国々では、米は野菜のように扱われています。日本では、米に野菜や魚介類などを加えて、塩や醤油で味付けして炊いたごはん料理の事です。
それでは歴史を見てみましょう!
■奈良時代
・あわ飯
食事の量を増やすため、粘り気のある「あわ」を米に混ぜていました。
・かて飯
「かて」とは米の節約のため量を増すものとして混ぜて炊く具のことあわの他、麦やひえなどの雑穀や野草、いも、大根などを混ぜていました。
→これが「炊き込みごはん」のルーツです!
■室町時代
・変わり飯
かて飯がごはん料理のひとつとしてもてはやされるようになった。米に麦、栗、豆、野菜などを入れて炊いたものです。
■江戸時代
・とり飯
・かき飯
えんどう飯、ねぎ飯、たけのこ飯、大根飯、とり飯、かき飯、かに飯など料理が増え、 味や季節感を楽しむ料理になりました。