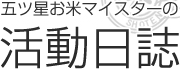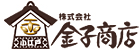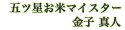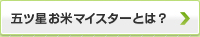カテゴリー
お店からのお知らせ
- 1月7日 「七草」粥で健康祈願!2026
- 2026年1月6日
- 謹賀新年 本年もよろしくお願いいたします。
- 2025年12月31日
- 今年もありがとうございました!2025
- 2025年12月30日
- 年内お届け!お年賀・帰省のお土産に
- 2025年12月28日
- お正月「のし餅」28日分 入荷しました
- 2025年12月27日
ごはんの歴史
2006年04月01日
今のような白いごはんを食べるようになったのは、江戸時代中期(18世紀)になってからです。それまで、もみがらを取っただけの玄米は半つき米(今の5分搗き)を主に食べていたんです。
■弥生時代
土器で、玄米を煮たり、蒸したりして食べた。
■奈良時代
土鍋で煮た水分の少ない固めのおかゆを食べるようになり、これが白いごはんのルーツ。
■平安時代
固がゆが、さらに水分が少なくなって飯としての姿を見せ、姫飯と呼ばれるようになる。
■鎌倉時代
金属の陶器の釜が広まり、「つば」のついた釜(羽釜)の登場で、調理も「煮る」から「炊く」に発展。
※ごはんを炊くとは、煮る・蒸す・焼く・蒸らすをあわせた調理方法なんですよ!
■江戸時代(中期)
厚手のふたをつけた釜が広まり、煮る・蒸す・焼く「炊き干し」法が定着。
★お米からごはんへ★
固いお米にも、水分が14%~15%含まれてます。(少なすぎて多すぎでもダメなんです!)
水を加えて加熱する事で、水分65%程度に仕上げることで、美味しいごはんとなるんです。