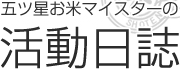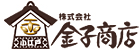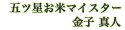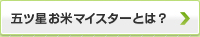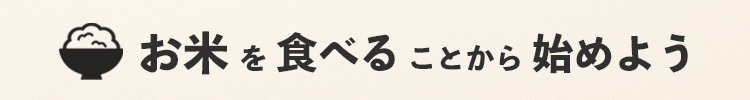カテゴリー
お店からのお知らせ
- 「高賀の森水」価格改定のお知らせ
- 2026年2月20日
- クレジットカード決済 メンテナンス 2/19・20・24
- 2026年2月18日
- 結の蔵「星空舞」キャンペーン開催中!
- 2026年2月17日
- お米の定期便《6回コース》開始しました!【3月末迄】
- 2026年2月16日
- 寒餅づくりに!新潟産こがねもち(特別栽培)
- 2026年1月22日
「令和の米騒動」第3弾 ~備蓄米の炊き方~
2025年06月06日
米不足が続くなか、「備蓄米の炊き方」に関するメディアからのお問い合わせが増えています。今回は、「令和の米騒動」シリーズ第3弾として、備蓄米の特徴やおいしく炊くための工夫をご紹介します。
農協による集荷量が全国的に減少するなか、昨年の収穫後には、産地から「契約取引」で予定していた数量も、集荷量の減少を理由に一部カットされるとの連絡が相次ぎました。この不足を補うため、「スポット取引」での調達が増加し、その結果、「スポット価格」は異常な水準まで高騰しました。
こうした状況のなか、政府が備蓄米の放出に踏み切ったことは、価格の過熱を抑える有効な対策のひとつとなりました。
実際、スポット価格は週ごとに下がり始めており、異常な高騰は抑えられつつあります。
しかし、備蓄米の放出は進められている一方で、産地からの輸送、精米工場での精米、袋資材の供給といった工程で「目詰まり」が発生しており、流通現場では十分に市場へ行き渡っていないのが実情です。
「まだ届いていない」という声を受けて、さらに備蓄米の放出が加速し、供給量が過剰になると、価格が急落するおそれがあります。
そうなれば、令和7年産米の価格にも大きな影響を及ぼし、かえって米の不足が解消されないまま、長期化する可能性も否定できません。
これまでの不足を受けて「契約取引分」の在庫も前倒しで消化されており、新米の入荷を前に、在庫が尽きかけている現場も少なくありません。当店でもやむを得ず数量制限をお願いしたり、すでに完売となってしまった銘柄米も多くなってきました。
🌾 備蓄米=“ひとつ品種”ではない
「備蓄米って、どんな味なんだろう?」と気になっている方も多いかと思います。
実際のところ、備蓄米には全国各地の産地・銘柄のお米が含まれており、それぞれに異なる特徴があります。
備蓄米には、非常に多くの産地・銘柄・年産・等級のお米が混在しており、「備蓄米」として提供される際には、これらを指定することはできません。順次出荷されるため、どのお米が届くかは事前には分からないのが現状です。
まさに、これだけの産地、銘柄のお米が“備蓄米”というわずか3文字でひとまとめにされている以上、ひとくくりに語ることは難しいのが実情です。
※実際にどの産地・銘柄が含まれているのかは、備蓄米(産地・銘柄)第1回~3回入札・随意契約で一覧にまとめています。
当然、産地や銘柄、品質、栽培方法によってお米の特徴も異なり、それに合わせた炊き方も変わってきます。
今後、「随意契約」による備蓄米についても、令和4年産(古古米)、令和3年産(古古古米)といった在庫が順次放出される見込みです。
備蓄米(令和4年産・3年産・2年産)【随意契約】申込数量 306,002トン
| 第1回(5/26) | 第2回(5/30) | 第3回(6/11) | 合計 |
| 212,535 | 44,270 | 49,197(20万トン予定) | 306,002(約15万トン申込中) |
※7/22更新
すでに政府備蓄米として約80万トンの放出され、今後、これが順次市場に流通していく見通しです。この数量は、近年の主食用米収穫量の減少幅(年間10〜20万トン前後)と比較しても、約3倍に相当する規模であり、需給に与える影響は非常に大きいと思います。
🩺古米化とは? 炊き方の“処方箋”
備蓄米は基本的に低温保管(15℃以下)されており、古米化の進行は比較的緩やかで、かつてのような著しい劣化は見られにくくなっており、まるで「冬眠している」ようなイメージです。
ちなみに、備蓄米ではありませんが、収穫後に籾のまま保管する「籾貯蔵」や、北海道などでの「超低温貯蔵(0℃以下)」も普及しており、鮮度や美味しさを追求している産地も増えています。
お米は呼吸をしているため、温度(穀温)が上がると、その呼吸が活発になり、結果として劣化が進みます。つまり、お米の大敵は、「高温・多湿」です。
そのため、家庭での保管も冷蔵庫の野菜室でジッパー袋などに入れて密閉し、低温倉庫と同等の温度環境を再現できる場所がおすすめです。保管温度を低く保つことで、呼吸を抑え劣化のスピードを抑えることができます。
すでに、臭いが気になるお米については、洗米の回数をいつもより増やし、冷たい水でお米の中心までしっかり浸漬させる方法が効果的です。
ただし、保管年数や作柄によっては、水分が抜けたり、デンプンや脂質が劣化することで、割れやすくなること、給水率の低下やご飯の硬さ、古米臭の発生など、炊きあがりに明確な差が出ることがあります。
特に「古古古米」になると、その状態には個体差が大きく、画一的な炊き方のアドバイスは難しいのが実情です。そのため、お米の状態に応じた“処方”を見極めることが、よりおいしく炊くための鍵となります。
🔍「古米化」による変化と対策
| 状況・特徴 | 対策例 |
|---|---|
| 水分が抜け給水しにくい | 炊飯水の水を増やして調整 |
| ご飯が硬くなる (デンプンの糊化抑制) |
・通常よりも5~10%多めの水で炊飯 ・冷水で30分~2時間程度浸漬 ※炊飯器によって異なる ※通常品質のお米に限る |
| ツヤが出にくい[透明度の低下] (タンパクの分子間相互作用による外観品質低下) |
「米油」を少量加えてみる |
| 古米臭(においが気になる) (脂肪が酸化「ヘキサナール」が発生 |
「酒」または「みりん」を少量加える |
| 旨みに乏しい | 「昆布」・「昆布粉」を加え、うま味補う ※銘柄米(古米)テスト:昆布1cm×1cmくらいが適量 |
古古米でも、近年の精米技術(糊粉層の除去など)により古米臭はある程度抑えられますが、酸化の進行により米質は全体的に硬くなっています。
目安としては、米2合に対して酒大さじ1杯+米油2〜3滴。これにより香りやツヤの改善が期待できます。ただし、加える量が多すぎると、お米本来の風味を損なう場合があるため、少量から試してみてください。
🍚それでも、古米臭が気になる場合
丼ものや肉料理、タレのあるおかずと組み合わせると臭いが目立たず、ごはんの食感も楽しめ、美味しく召し上がれると思います。
また、多くの炊飯水で、硬い米粒の中まで水が浸透し、しっとりと滑らかな食感になります。ただ、火力の弱い炊飯器では、水が増えた分、十分に短時間で飛ばしきれず、全体的に柔らかく、水っぽい仕上がりになってしまいます。
そのため「火力の強い炊飯器」であれば、多めの水でお米粒に浸透させながらも、沸騰時には余分な水分をしっかり蒸発させるため、硬い米でも、ごはんにハリとツヤ、甘みが生まれ、美味しく炊きあがります。
※炊飯器の炊飯目盛りは、機種によって設定されている水の量が異なります。
🧑🍳簡単にできる“ブレンド”という工夫
今、出回っているお米は、「比較的新しい原料のお米」でそれほどの差を感じない場合もあります。
とはいえ、どうしても口に合わない、または炊き方の工夫が難しいと感じる場合は、令和6年産米とブレンドする方法もおすすめです。
たとえば、3合炊く際に、
「備蓄米2カップ」+「令和6年産1カップ」
のようにブレンドすると、全体の味わいがぐっとまとまりやすくなります。
備蓄米は、震災や不作、今回のような米不足といった非常時の供給を支える“セーフティネット”として、重要な役割を果たしています。
一方で、銘柄や産地を選べない制約があるため、調理にはひと工夫が求められます。
これまで、全国の産地では、ブランド化競争の中で美味しいお米づくりに取り組み、栽培方法を研究したり、「もっと美味しいお米が作れないか」、「高温対策をしながら、品質の高いお米ができないか」と特色あるお米づくりに挑戦し、創意工夫とたゆまぬ努力を重ねてきました。
しかし、備蓄米のように「国産米なら何でもよい」、「5キロで2000円台」という意識が広がってしまえば、真摯に“おいしいお米づくり”を追い続けてきた生産者などの努力が報われなくなってしまいます。
現在、生産現場では燃料費、肥料、人件費などのコストが高騰し、これまで以上に厳しい状況に置かれています。そのため価格に見合った生産が難しくなり、結果として増産を断念したり、離農される生産者も増えています。
実際、主食用米の収穫量は、平成20年の865万トンから令和6年(概数値)の約679万トンへと、この16年で約200万トン減少しました。これは一時的な要因だけでなく、長引く米価の低迷が大きな要因と考えられます。
お米は、年に一度しか収穫できない農産物です。
今こそ、日常的にお米をしっかり食べ、消費量を維持・増加させていくことが、将来の安定した米づくりにつながると信じています。