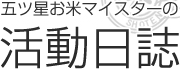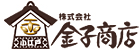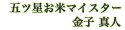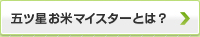カテゴリー
お店からのお知らせ
- 1月7日 「七草」粥で健康祈願!2026
- 2026年1月6日
- 謹賀新年 本年もよろしくお願いいたします。
- 2025年12月31日
- 今年もありがとうございました!2025
- 2025年12月30日
- 年内お届け!お年賀・帰省のお土産に
- 2025年12月28日
- お正月「のし餅」28日分 入荷しました
- 2025年12月27日
「もち米」の歴史
2006年04月03日
日本での「もち」の歴史は古く、稲作の伝来とともに東南アジアから伝わってきたと考えられています。
平安時代になると、白い「搗き餅」の他に、大豆や小豆、ごまなどの材料を加えた餅や、米の粉を用いた「ちまき」のような「粉もち」などが作られていました。
■鏡餅
鎌倉、室町時代になってから使われ始めましたが、平安時代にはもち鏡と呼ばれていたとされています。
古来、鏡は霊力を備えたものとして扱われ、餅は神聖な力がこもる食べ物と考えられていました。
そのもちを神の宿る鏡に見立てて形作られたといわれています。
■力もち
江戸時代には、餅を年中行事などにも作って祝う事が広まり、諸国の街道筋では食べると力が付くと言う「力もち」のような名物もちが売られるようになりました。