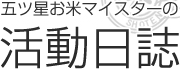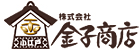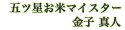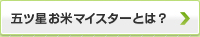カテゴリー
お店からのお知らせ
- 1月15日「小正月(こしょうがつ)」2025
- 2026年1月13日
- 1月11日 「鏡開き」 2026
- 2026年1月9日
- 1月7日 「七草」粥で健康祈願!2026
- 2026年1月6日
- 謹賀新年 本年もよろしくお願いいたします。
- 2025年12月31日
- 今年もありがとうございました!2025
- 2025年12月30日
カテゴリー「お米の歴史と文化」に含まれる記事
-
「炊き込みごはん」の歴史
炊き込みごはんは、米の収穫が十分でなかった頃、米を節約するために色々な具を混ぜて炊いたのが始まりです。 欧米諸国など、穀物としては主に小麦を原料とした食べ物を食べている国々では、米は野菜のように扱われています。日本では、米に野菜や魚介類などを加えて...
-
「すし」の歴史
すしは「酢し」、つまり、すっぱいものという意味からきた言葉で、「鮨」などの漢字が使われています。 魚の字が使われているのは、「すし」が魚の保存方法から生まれたからです。 ■弥生時代(なれずし) ルーツは、東南アジアの「なれずし」といわれています...
-
「おにぎり」の歴史
すでに弥生時代の中ごろにはあった事が、遺跡の発掘から分かっています。 平安時代にはおにぎりは、兵士の食事として用いられていました。 おにぎりは、もともと「もち米」を蒸してにぎったものが原型ですが、鎌倉時代の末期になると主に、うるち米(普通の白米の...
-
「もち米」の歴史
日本での「もち」の歴史は古く、稲作の伝来とともに東南アジアから伝わってきたと考えられています。 平安時代になると、白い「搗き餅」の他に、大豆や小豆、ごまなどの材料を加えた餅や、米の粉を用いた「ちまき」のような「粉もち」などが作られていました。 ■...
-
ごはんの歴史
今のような白いごはんを食べるようになったのは、江戸時代中期(18世紀)になってからです。それまで、もみがらを取っただけの玄米は半つき米(今の5分搗き)を主に食べていたんです。 ■弥生時代 土器で、玄米を煮たり、蒸したりして食べた。 ■奈良時代...