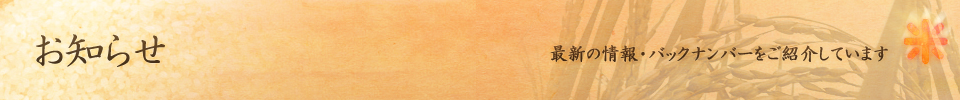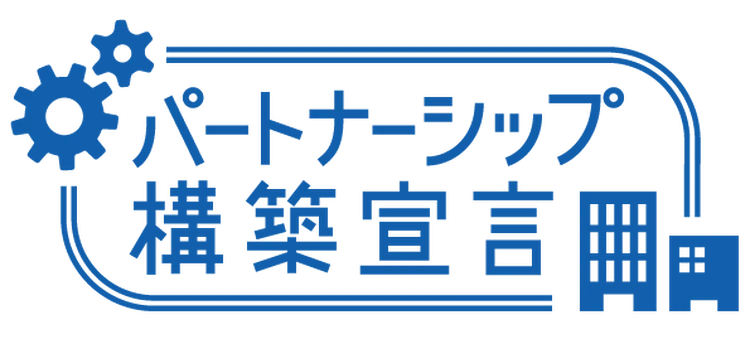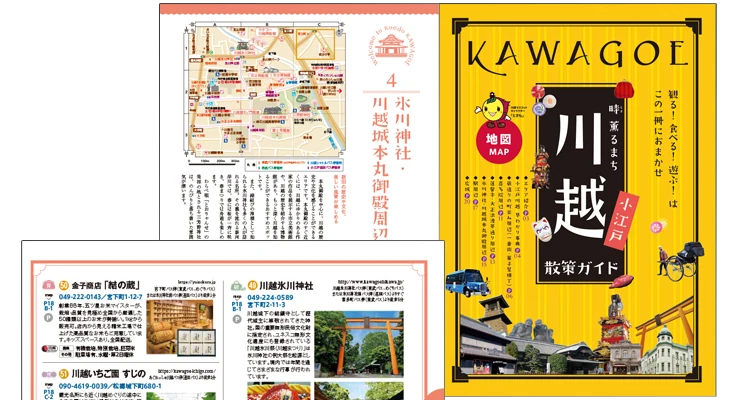お店からのご案内
| 2025年05月20日 | 「会員ステージ」不具合分を修正・正常に反映しました毎度ご利用いただきまして誠にありがとうございます。 会員ステージ機能において、一部のお客様のステージが本来より下がって表示されていた事象が発生しておりました。 このたび、該当のお客様のステージ情報の修正が完了いたしましたので、ご報告申し上げます。 ご不便・ご心配をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。 引き続き、当店をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
|---|---|
| 2025年05月20日 | 「会員ステージ機能」一部不具合について毎度ご利用いただきまして誠にありがとうございます。 会員ステージ機能において、一部のお客様に対し、購入期間に基づくステージ更新処理の過程で、本来のステージよりも下がって反映されてしまう事象を確認いたしました。 現在、原因を確認のうえ、システム会社と連携し、すでに対応を開始しております。 お客様にはご迷惑・ご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 引き続き、当店をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
| 2025年05月20日 | メンテナンス完了(クレジットカード決済) 5/20毎度ご利用頂きまして誠にありがとうございます。 お米通販ショップのクレジットカード決済メンテナンスに伴い、下記の時間帯でクレジットカード決済が一部エラーとなる可能性がございましたが、メンテナンスが完了致しました。 メンテナンス日時(お米通販ショップ決済システム)2025年5月20日(火) AM 1:00 – AM 6:00 |
| 2025年05月19日 | クレジットカード決済 メンテナンス 5/20毎度ご利用頂きまして誠にありがとうございます。 ◆対象:クレジットカード決済 ◆日時:2025年5月20日(火) AM 1:00 – AM 6:00 ◆備考 ・クレジットセンターでエラーが検知されました。再度、または、しばらく時間をおいてから操作して下さい。 ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、上記の時間帯を避けてご利用頂きますようお願い致します。 メンテナンス日時(お米通販ショップ クレジットカード決済システム)2025年5月20日(火) AM 1:00 – AM 6:00 |
| 2025年05月16日 | メンテナンス完了(クレジットカード決済) 5/16毎度ご利用頂きまして誠にありがとうございます。 お米通販ショップのクレジットカード決済メンテナンスに伴い、下記の時間帯でクレジットカード決済が一部エラーとなる可能性がございましたが、メンテナンスが完了致しました。 メンテナンス日時(お米通販ショップ決済システム)2025年5月16日(金) AM 1:00 – AM 6:00 |
| 2025年05月15日 | クレジットカード決済 メンテナンス 5/16毎度ご利用頂きまして誠にありがとうございます。 ◆対象:クレジットカード決済 ◆日時:2025年5月16日(金) AM 1:00 – AM 6:00 ◆備考 ・クレジットセンターでエラーが検知されました。再度、または、しばらく時間をおいてから操作して下さい。 ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、上記の時間帯を避けてご利用頂きますようお願い致します。 メンテナンス日時(お米通販ショップ クレジットカード決済システム)2025年5月16日(金) AM 1:00 – AM 6:00 |
| 2025年05月08日 | 「パートナーシップ構築宣言」お知らせ株式会社 金子商店は、内閣府、中小企業庁などが推進する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、「パートナーシップ構築宣言」を公表いたしました。 当社は今後もサプライチェーンのお取引先様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進め、新たなパートナーシップを構築してまいります。 「パートナーシップ構築宣言」(株)金子商店(PDFファイル) 当社のパートナーシップ構築宣言は、下記ポータルサイトでもご確認いただけます。 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(外部サイトリンク) |
| 2025年04月25日 | ゴールデンウィーク 営業日 2025 毎度ご利用頂きまして誠にありがとうございます。 4月30日(水)定休日 4月29日、5月1日、2日、5日、6日は営業いたします。 休業期間中の発送及びお問い合わせに対するご返答は5月6日以降に順次行います。また、5月3日~5日までのご注文は、5月6日(火)より発送いたします。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
| 2025年04月21日 | 小江戸川越散策ガイドに「結の蔵」掲載最新版「小江戸川越散策ガイド」に『結の蔵』が、氷川神社・川越城本丸御殿周辺のお買い物スポットとして紹介されています。 川越にゆかりのある作家の作品を展示している市立博物館や縁結びの神様として人気の氷川神社など、川越の歴史や文化を感じられるエリアです。 マップには巡回バスの停留所も表示してあり、川越の散策に役立つ情報が満載です。川越にお越しの際はぜひご活用ください。 公式HPからはマップのダウンロードができます。⇒小江戸川越観光協会(公式) |
| 2025年04月18日 | メンテナンス完了(通販ショップ) 4/18毎度ご利用頂きまして誠にありがとうございます。 お米通販ショップの決済システムメンテナンスに伴い、作業期間中、下記の対象決済において繋がりにくい時間帯がございましたが、メンテナンスが完了致しました。ご協力頂きまして誠にありがとうございました。 メンテナンス日時(お米通販ショップ決済システム)2025年4月18日(金) AM 1:00 – AM 6:00 |