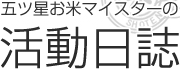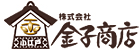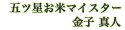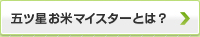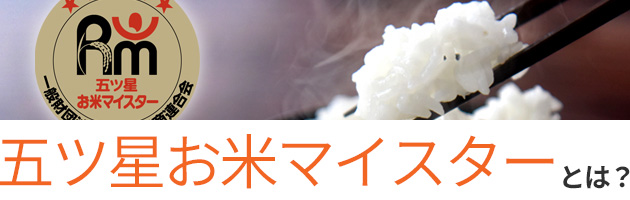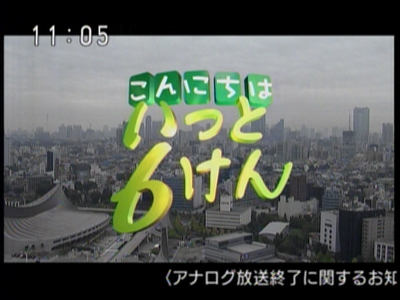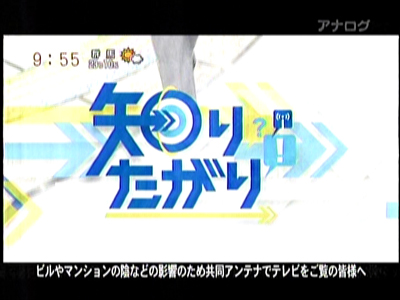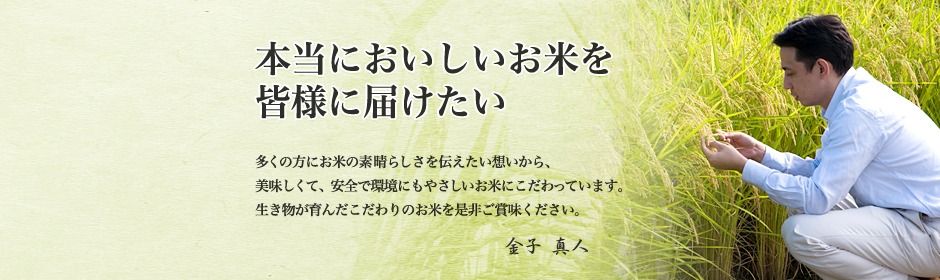
カテゴリー
お店からのお知らせ
- 「高賀の森水」価格改定のお知らせ
- 2026年2月20日
- クレジットカード決済 メンテナンス 2/19・20・24
- 2026年2月18日
- 結の蔵「星空舞」キャンペーン開催中!
- 2026年2月17日
- お米の定期便《6回コース》開始しました!【3月末迄】
- 2026年2月16日
- 寒餅づくりに!新潟産こがねもち(特別栽培)
- 2026年1月22日

お米マイスター金子真人の食育・講演活動、産地情報、品種の紹介、お米の栄養や歴史など様々な情報をお届けします。
お米マイスターの活動 産地訪問 お米の品種 お米の知識
 最新の活動日誌
最新の活動日誌
-
こんにちはいっと6けん(NHK) 生出演
生活情報番組「こんにちはいっと6けん(NHK)」の新米特集に、お米マイスターが生出演しました。 【放送日】 10月25日(月曜日) こんにちはいっと6けん 総合 月~金 11:05~11:54 新米をおいしく食べよう ...
-
暑さに強いお米(高温耐性米)
出穂(しゅっすい)・登熟する8月を中心に全国的に異常な高温が続き、過去113年間で最も暑い夏(6月~8月)となり、9月に入っても猛暑記録が各地で更新されるなど、猛暑は終わりを見せないまま収穫に入りました。 その影響で高温障害(特に真っ白なお米)によ...
-
知りたがり「主婦達への道」(フジテレビ)生出演
フジテレビ「知りたがり」で、主婦の達人になるために様々なお役立ち情報をお伝えするコーナー「佐々木恭子の主婦達への道」に、お米マイスターが生出演しました。 【放送日】 2010年10月18日(月) メインキャスター:伊藤利尋 ゲスト:秋野暢子、...
-
22年産米について 電話取材(TV・ラジオ)
22年産のお米について、おはよう日本(NHK)、TBSラジオから電話取材がありました。 過去113年間で最も暑い夏となった今年は、稲作にも影響が出ており、お米の等級が下がっています。しかし、お米は、1個単位の農産物とは違い、粒の集まりですので等級が...
-
J-WAVE 81.3FMラジオ取材
FMラジオJ-WAVE(81.3)から、新米の取材を受けました。 10月から新しく始まった新番組「I A.M」の、食がもっと楽しくなる美味しい情報をお届けするコーナー「7-ELEVEN FAVORITE DISH」にお米マイスターが登場し、お米の炊...
-
COP10提言(生物の多様性を育む農業)
生物多様性条約台10回締約国際会議へ、第1回生物の多様性を育む農業国際会(ICEBA/1)からの提言にお米マイスターも推進してます。 2010年7月2日から4日まで、農業の生物多様性を推進しようとする日本・韓国・中国の農業者・研究者・消...
-
ごはんパワー教室(高階中学校)
お米マイスターの食育出前授業「ごはんパワー教室」で、お米の授業に行ってきました。 日時:10月1日(金)10:00~12:00 場所:川越市立高階中学校 特別支援学級 フィリップを使ってお米について学んでもらいました。 お米の...
-
魚沼産コシヒカリの収穫「新潟へ」
新潟高柳を後にして、南魚沼コシヒカリの収穫確認へ行きました。 今年は例年になく、気温が高かったので、全体的に等級が落ちてしまいました。 品質の部分は、産地で選別したり、当店で精米するときにふるい、近赤外線による選別をすることで品質を上げることがで...
-
新潟コシヒカリ(棚田)の収穫「新潟へ」
企業のキャンペーンで使うお米の収穫確認に、新潟へ行ってきました。 今年は気温が高く、来る途中、稲のが倒伏が目立ってましたが、この棚田は倒れることなく、丈夫に育っていました。 棚田百選認定(花坂の棚田) 倒伏もなく、丈夫に育ってました。 ...
-
ごはんの栄養素
お茶碗1杯のごはんには、たくさんの栄養素が詰まっています。 ごはん1杯(150g)=252kcal たんぱく質 3.8g 体をつくり、エネルギーのもとになります。 脂質 0.5g 体の細胞をつくり、少ない量でも大きなエネルギーの...