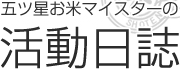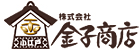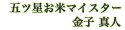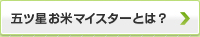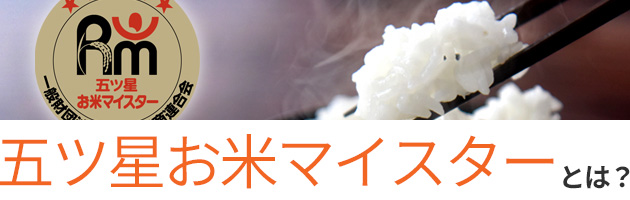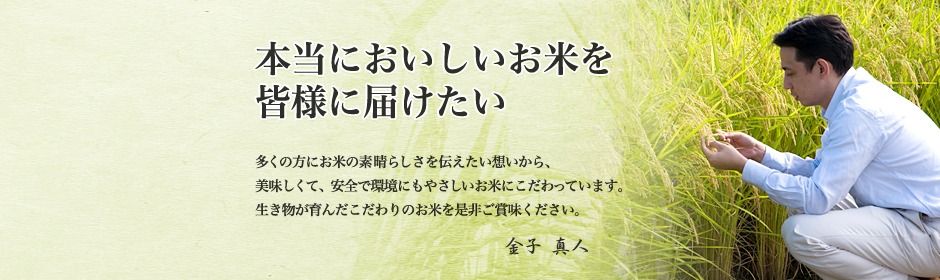
カテゴリー
お店からのお知らせ
- 「高賀の森水」価格改定のお知らせ
- 2026年2月20日
- クレジットカード決済 メンテナンス 2/19・20・24
- 2026年2月18日
- 結の蔵「星空舞」キャンペーン開催中!
- 2026年2月17日
- お米の定期便《6回コース》開始しました!【3月末迄】
- 2026年2月16日
- 寒餅づくりに!新潟産こがねもち(特別栽培)
- 2026年1月22日

お米マイスター金子真人の食育・講演活動、産地情報、品種の紹介、お米の栄養や歴史など様々な情報をお届けします。
お米マイスターの活動 産地訪問 お米の品種 お米の知識
 最新の活動日誌
最新の活動日誌
-
韓国 国営放送「KBS」取材(2日目)
昨日に引き続き韓国KBSテレビの取材を受け、今日は、当店のお米をご利用頂いているお客様(飲食店・ご家庭)や、当店の契約農家の方にご協力頂きました。 ■放送日(5月23日・24日 2日連続) ・KBS 第1チャンネル 18時~ (全国18ネット)...
-
韓国 国営放送「KBS」取材(1日目)
韓国の国営放送KBSの取材を受けました! 今、韓国では日本の高品質な米づくりに興味をもたれ、日本の稲作、流通について何を学ぶべきものなのかを放送されるそうです。 13日は店舗、玄米倉庫、精米、包装、食味分析など説明し、明日(14日)は当店のお客様...
-
ミニ田んぼに水が入りました!
ミニ田んぼに水を入れてたのですが、どんどん吸収してしまいどこまで入るのだろうと不安になってしまいました。(約15分)そして水が溢れそうになったので終わりかと思い土を掘り返したら底から乾燥した土が出てきました。 すべてを掘り返し、もう一度水を入れたの...
-
旬な食材をおかずに!
日本は、四季折々の食べ物たがたくさん作られる恵まれた国です。 旬の食べ物は、味も良く、もちろん栄養分もたっぷりです。 体にも環境にもやさしい食事ができますのでお試しを! ■春 さわら、アサリ、アスパラ、イチゴ、たけのこ ■夏 シマアジ...
-
ここ掘れ!ワンワン
今朝、土を入れたミニ田んぼの土が外に飛び出して数箇所穴が掘ってありました。 驚いているとき、愛犬の顔、足にいっぱいの土が付いててやったのは間違いなく愛犬でした。 その防御として、水を張ろうと思い農家の方に聞いたら、今水を入れてしまうと硬くなってし...
-
大事な土なので買ってきました。
契約農家の方に、「田んぼから土をとってもいいよ」といわれたのですが軽トラック1台分となると時間がかかりとても仕事の合間にできなかったので、購入してきました。 合計で20袋、アッというまに使ってしまいました! 農家の方はお金がかかるという事は知って...
-
稲を植える場所づくり
2日間かけて、ゴミ拾いも終わり稲を植える場所づくりをしました。 穴を掘り、回りを囲い、水が浸透しないようにビニールを敷き、掘った土をいれて準備OK。 念のため、農家の方に聞いたら、「この土では育たない!」と助言してもらい、失敗するところでした。 ...
-
今日から稲作に挑戦!
昨年は、プランターで稲作をしましたが、今年はもう少し広い場所で挑戦してみます。 場所があまり無いので、今までゴミが置かれていた場所に決めました。今日はゴミ拾いとブロックで回り固めました。 普段は、パソコンに向かう時間が多いので、耕すのは一苦労でし...
-
お米にも花が咲くの?
あまり見かける事ができないお米の花は、稲穂に咲きます。 1つの穂にだいたい100個以上の花が咲くんですよ。 お米の花が咲くのには、光と温度条件が必要で、午前9時半頃からお昼くらいまでの2時間で咲いて閉じてしまいます。 昨年、花を写真で撮るため何...
-
どんなお米が生産されているの?
どの品種のお米がいっぱい作られているかご存知ですか? もちろん1位はコシヒカリ(37.7%)です。 この品種を知らない人はいないですよね。 その後は何だと思いますか? ・ ・ ↓ 答えは、 2位 ひとめぼれ (10.5%) ...