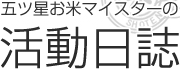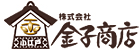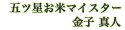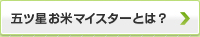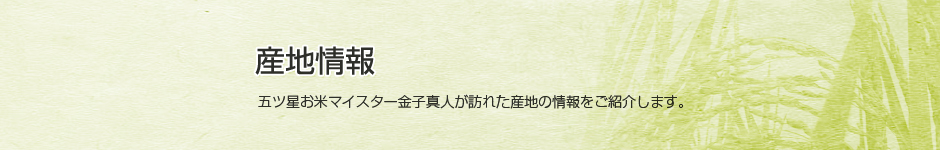
カテゴリー
お店からのお知らせ
- おいしいごはんの秘訣「お米の保存・炊き方」
- 2025年5月30日
- メンテナンス完了(クレジットカード決済) 5/28
- 2025年5月27日
- クレジットカード決済 メンテナンス 5/28
- 2025年5月27日
- 国産長粒米で簡単&本格アジアン料理
- 2025年5月27日
- メンテナンス完了(クレジットカード決済) 5/27
- 2025年5月26日
「金色の風」岩手県奥州市へ
2023年10月19日
「金色の風」サポーターの産地見学ツアーが岩手県県南広域振興局の主催で開催され、行政・生産者の方と意見交換を行いました。
午前中は常盤小学校5年生の課外授業に参加し、長年やりたかった、昔ながらの脱穀が体験できました。
千歯こき


江戸時代から昭和の初期頃まで使われた農機具で、櫛のように並んだ歯の間に稲穂を通して引くと、籾が落ちる仕組み。
足踏み脱穀機


ペダルを踏んでドラムを回転させ、V字型の針に稲穂を触れさせると籾が落ちる仕組みです。明治時代に登場し、千歯こきよりも効率よく籾が落とせるようになりました。
唐箕(とうみ)


籾に混ざったごみ(もみ殻やわらくず)などを風力で吹き飛ばし、選別する仕組み。
ハーベスター

脱穀を専門に行う農業機械で、稲を投入すると籾は左側の袋に、残りのわらは一定量をひもで縛って排出される仕組み。時代と共に農機具が進化していることを感じます。
現代のコンバイン(回転刃の部分)

稲の刈取りから脱穀、選別まで同時に行うことができます。現代の稲作には欠かせない機械ですが、費用の負担が大きくメンテナンスも必要です。
昔の農機具と比較すると、足踏み脱穀機のようなV字型の針で脱穀し、唐箕のように風を送って選別をしている点では同じ仕組みを用いていることが分かります。昔の人々の知恵と工夫で稲作が発展できたことを実感しました。
南部鉄器の工場見学(及源鋳造)
約900年の歴史をもつ南部鉄器、表面のぶつぶつした模様は霰(アラレ)といい、表面積を増やして保温性を高めているそうです。
昔は鉄鉱石ではなく、砂鉄を集めて鉄(たたら製鉄)にしていました。

たたら製鉄
不眠不休で3~4日間砂鉄と木炭を交互に入れ銑鉄等を製産していました。投入される量は、砂鉄10トンに対し木炭も10トンとその量だけ見てもとても大がかりな作業な事がうかがえます。